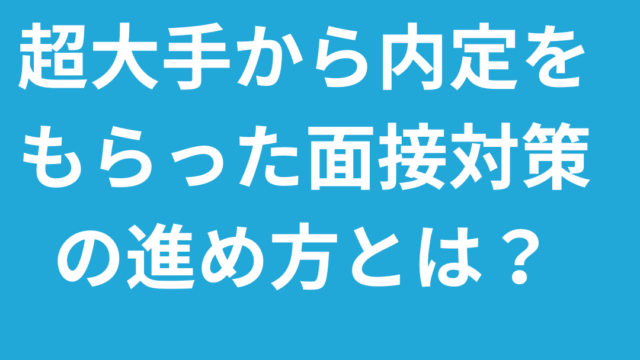年俸制の会社で働くメリットやデメリットってなんだろう?
年俸制だと残業代とか賞与ってどうなるの?
こんな疑問にお答えしていきます。
企業からお金をもらう仕組みとしては年俸制と月給制とに分けることができ、それぞれに違いがあります。
ただ、結論から言えば、月給制なのか年俸制なのかが転職先を決める上での重要な判断基準になるケースはほとんどないと言って良いでしょう。
詳しく解説していきます。
年俸制とは

年俸制とは、企業からもらうお給料が月額ではなく年額で決まっている形態のことで、外資系企業で多く見られます。
月給制は毎月のお給料が決まっており、賞与(ボーナス)が業績によって変動しますが、年俸制ではそうした変動が原則ありません。
例えば、年俸600万円という契約で企業で働いている人は、600万円÷12ヶ月で毎月50万円がお給料として支払われる形になります。
残業代は出るの?
もし年俸制の会社で残業をした場合、残業代は出るのでしょうか。
年俸制の企業の場合でも法的には残業代を支払う義務があります。
法的には、とあえて書いたのは現実には支払わない企業もあるためです。
ただ、残業代を支払わない企業を見分けることは困難です。
あえて傾向を上げるとするなら、初めから年俸が高い企業は残業代を支払わない可能性が高いです。
「残業も含めた金額」として提示している面もありますし、そもそもプロ野球選手などは年俸制ですが試合で延長したからと言って残業代が出ないのと同じイメージかと思います。
とある外資系コンサルティングファームなどでは以前は支払われなかった残業代を支給することにしたとらしいですが、それで実際に残業代を受け取る従業員はほとんどいないと言われています。
馬鹿正直に残業代を申請しても会社にいづらくなるだけだからです。
年俸制の企業の考え方はペイフォーパフォーマンスであり、ようは成果を出した人材にはたくさん払いますよ、というスタンスです。
残業は長時間働いたというだけであり、成果を示すことには繋がりません。
特に、年俸制を導入している企業が多い海外では残業は悪という考えもあるので、年俸制の企業で残業代を期待するのはあまり得策ではないかもしれません。
賞与は出るの?
年俸制の会社で賞与は出るのでしょうか。
賞与は出す企業と出さない企業とに分かれます。
賞与を出さない企業は年俸額÷12の金額を毎月支給する形ですが、賞与を出す企業だと年俸額÷16の金額を毎月支給し、夏と冬のボーナスとして2ヶ月ずつ支給する、みたいな形になります。
ボーナスを夏冬1ヶ月ずつ支給する企業であれば、年俸額÷14が毎月支給されます。
年俸制を導入している企業は?
年俸制を導入している企業は特に珍しくなく挙げればキリがありませんが、いくつかピックアップしてご紹介します。
・アマゾンジャパン
・野村総合研究所
・LINE
・日本IBM
・コストコ
・ウォルト・ディズニー・ジャパン
また、年俸制は全従業員一律で導入されるわけでもなく、上記の例で言えばコストコは管理職になってから年俸制が適用される仕組みとなっています。
年俸制のメリット

年俸制の会社で働くメリットとしては、大きく以下の二つがあります。
・年間でもらえる額が決まっているため生活が安定する
・年収が同じでも毎月の手取りが多くなりやすい
まず一つ目が年間でもらえる額が決まっている点。
月給制で賞与の額が大きく変動する会社の場合、賞与の支給額によって年収が大きく変動してしまいます。
そうなると、「最悪もらえないかもしれない」リスクもあるため生活の設計が難しくなります。
また、2つ目のメリットとして毎月の手取り額が多くなりやすいという点が挙げられます。
月給制で年収に占める賞与の比率が高い企業だと、毎月の給料は少なめになってしまいますが、年俸制だと同じ年収でも賞与の比率が低く、その分毎月の給与が高くなることが多いです。
転職にあたっては「毎月の手取金額」を重要視して転職する人も多く、家族やマイホームなど、支出が嵩む世代にとっては重要なポイントとなります。
年俸制のデメリット
一方、年俸制のデメリットとしては、その年に頑張っても賞与などで還元される機会がないことでしょうか。
年収を上げたいのであれば、成果を出して職位や等級を上げる必要があります。
また、年俸制の会社は傾向として年功序列よりも実力主義の社風であることが多いです。
実力のある人にとっては年収を上げていきやすいですが、そうでない人にとっては減俸や最悪の場合にはリストラがありうるという点は覚悟しておいた方が良いです。(年俸制のデメリットというよりは、年俸制を導入していることが多い外資の特徴という方が適切かもしれません。)
まとめ
年俸制は外資系企業では当たり前の形態ですが、日系企業でも導入している企業は多数あります。
転職先を適当に選ぶのではなく、給与の支払い形態の違いも含めて総合的に考えるようにしましょう。