・最終面接の対策をしたい
・最終面接で質問される内容を知りたい
・最終面接で逆質問で何を聞けば良いかわからない
こんな疑問やお悩みにお答えしていきます。
最終面接でどんな質問をされるのかは企業によって様々。
ただ、共通していることとしては面接官が社長や取締役といった役員クラスであるということ。
そうした面接官の属性から対策を練ることはできるので解説していきます。
最終面接対策ですべきこと
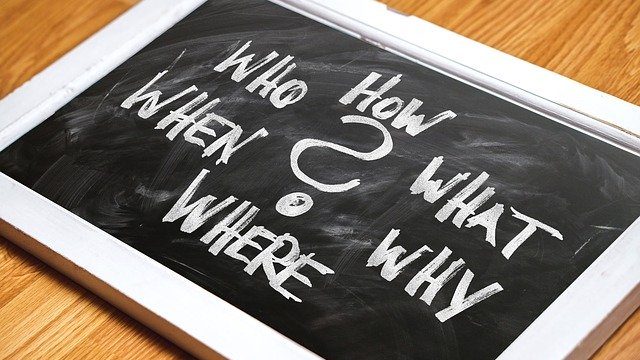
面接回数は企業によってまちまちで、1回だけで終わることもあれば5回以上面接をすることもあります。
ただし、最終面接ではいずれも役員が出てくるという点においては共通しています。
つまり、最終面接対策とは役員面接対策と言い換えることができます。
面接対策をする上では、最後の面接かどうかが重要なのではなく、面接官が誰なのかが重要なのです。
そして、役員面接の対策としては以下のような印象を相手に持ってもらえるように準備することがポイントです。
・長く定着してくれそうだと思われること
・既存の社員との相性が良さそうだと思われること
・会社を良い方向へ変えてくれそうだと思われること
直属の上司レベルであれば今困っている実務面の課題を解決してくれるかどうかを重視するでしょうが、役員の関心ごとはもっと長期的な視点です。
役員は会社の5年後10年後も見据えて計画を練るのが仕事なので、その観点から人材採用においても長期的に会社に貢献してくれそうかについて評価されることになります。
長期的に貢献してくれる人材にはスキルだけでなく人物面も会社に会うことが重要であり、役員が面接官として出てきた場合にはあなたがどんな人柄なのかを面接を通じて深く知ろうとすることでしょう。
そして、役員からプラスの印象を持ってもらえるようにするためには以下の準備を徹底することが重要です。
・自己分析がしっかりとできていること
・企業研究がしっかりとできていること
・求人理解がしっかりとできていること
自己分析や企業研究というと就職活動のようですが、転職活動でも重要性は変わりません。
転職(企業にとっては採用)とは相性の問題が全てです。
誰にとっても良い企業もなければ、誰にとっても悪い企業もありません。
逆に、どの会社にも合う人もいませんし、どの会社にも合わない人もいません。
転職(あるいは採用)はあくまで相性が良い相手と巡り合えるかどうかが重要であり、相性の良さを見極める上では自分自身の理解と企業の理解をどちらも深める必要があるわけです。
自己分析や企業研究はどこまでやっても終わりはありませんが、転職活動の場合は時間的な制約があるため時間の許す限り行うようにしましょう。
ちなみに、日系企業の場合だと求人票の内容が明確になっていないこともあるので、その場合には自己分析と企業研究だけしっかりとしておけば内定はもらえます。(求人票が明確になっていない状態で転職して幸せになれるかどうかは別問題ですが。)
外資系企業の場合は募集ポジションごとにミッションや業務内容、求められるスキルが全て明確に定義されている点が日系企業と違う点です。
自己分析、企業研究、求人理解はそれぞれ以下の観点で行うと良いです。
・自分の過去の行動や判断全てについてそれを選んだ理由を答えられる(他の選択肢を選ばなかった理由が明確にわかっている)
・自分が優先したいこととそのために妥協できることが何かわかっている
・自分の強みと弱みがわかっている
・その企業が進もうとしている方向を理解している
・その企業が今ぶつかっている課題を理解している
・募集ポジションがどんなミッションを背負うことになるのか理解している
・募集ポジションのミッションを達成する上で、自分が最適な人材であるという確信が持てている
こうした状態になるまで準備をしていれば最終面接を通過する確率をグッと高くなります。
また、仮にそれで不合格になったとしても、それはあなたが劣っているから落ちたのではなく、その企業と合わなかっただけだと割り切れば大丈夫です。
一番悔しいのが「準備不足で落ちる」ことですからね。
入念に自分の理解と企業の理解、そして求人の理解を深めていくようにしましょう。
最終面接で質問されるのはビジョン
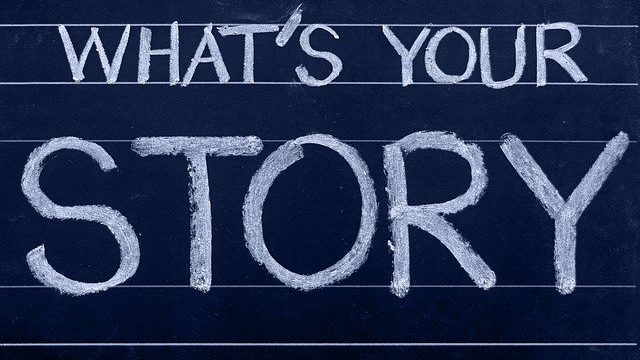
最終面接で聞かれる内容を一言で表現するなら「候補者のビジョン」についてです。
実務をこなせるスキルがあるのかどうかは最終面接より前の選考でおおよそ評価は終わっています。
それに最終面接で出てくる役員は実務面まで把握していないことが多いので、質問されて回答したとしても面接官自身がよく理解できないでしょう。
そうなると必然的に人柄を確かめる質問が多くなり、人柄を知るためにされるのがその人の志や将来のプランなどになるわけです。
最終面接の対策をするのなら、これまでどういう人生経験(成功や失敗)を積んできて、それぞれの節目で何を考えどう行動し、それを踏まえて今後はどうしていきたいのか、について考えを整理するようにしましょう。
仕事に関することはもちろんですが、仕事はあくまでも人生の中で一部に過ぎません。
仕事に限らず人生全体での過去・現在・未来についての考えを整理する必要があります。
・あなたは将来どうなりたいのか?
・将来のプランの中で当社で働くことはどういう位置づけなのか?
・これまでで一番大きな決断は何か?
・なぜその時その決断に至ったのか?(なぜ他の選択肢を選ばなかったのか?)
逆質問では何を聞くべきか?

もし最終面接で逆質問の機会が与えられた場合には面接官に何を聞けば良いでしょうか?
逆質問の目的は評価の向上と企業理解
まず、逆質問をする目的としては大きく以下の2つがあります。
・質問を通してこちらの評価を高める
・質問への回答を通して企業理解を深める
面接官はこちらがどんな質問をしてくるかによって能力や人柄を図ろうとしてきます。
例えばどんな面接官相手にも「残業は多いですか?」とか「ボーナスはちゃんともらえますか?」といったことばかり質問してしまうと「仕事をやる気がない」と判断されてしまう可能性があります。
また、せっかくの質問の機会にはきちんと自分が知るべきだと考える重要な事柄についても明確にするチャンスです。
内定をもらえたとしても、判断材料がない中では正しい選択ができません。
なので、逆質問では自分の評価を高めるための質問、そして、内定をもらえた場合に承諾するか否かを判断するために必要な情報収集のための質問という2つの観点で準備する必要があります。
さらに、これらの目的を達成するためにも、相手が役員クラスであることを踏まえて逆質問で聞く内容を考えなくてはなりません。
例えば、現場の責任者クラスの方が面接官であれば実務に関することや、配属先のチームに関することなど自分の仕事に直結する内容を質問すれば良いでしょう。
しかし、役員面接でそうした細かいことを聞いても相手は答えられない可能性がありますし、基本的に人間というのは自分が答えられない内容を質問されることを嫌います。
役員面接で細かな実務に関連する内容を聞いてしまったら印象を悪くしてしまう可能性があるので注意しましょう。
なので、業務内容ではなく組織や会社についてなど、やや質問の抽象度を上げた質問する方が良いです。
例えば、「募集部門の組織の課題はどこだと思うか?」などです。
また、組織自体についてではなく機能について質問するのも有効です。
例えば営業部の課題はどこだと思いますか?は組織についての質問ですが、営業面での課題はどこだと思いますか?という聞き方にすれば営業機能全体についての考えを聞くことができます。
得られるであろう回答も以下のように違ってくるはずです。
・ベテランが多い反面次の若い世代が育っていないこと
・人数が少なく需要に対応し切れていないこと
・競合の方が価格が安く、見積もりで比較されると負けることが多い
・顧客数は伸びているが解約率が高い
人材採用とは経営課題を解決する手段として行われるものです。
経営課題を理解することは、自分に求められる役割を理解することにも繋がるほか、役員が今の会社の現状をどう捉えているのかを知る良い機会にもなります。
組織課題や事業課題をヒアリングすることでその会社の社風も感じれることができますし、求人という狭い範囲に囚われずに質問を考えるようにしましょう。
逆質問の注意点
逆質問の内容を考える上で注意したいのが公表されている情報ではないか?という点です。
もし上場している会社の場合には組織や会社の中長期計画について説明会資料などで公表している可能性が高いです。
公表資料に載っている情報を質問するのは企業研究不足の証として不利になることが多いのでやめましょう。
また、仮に上場していない場合でも社長や社員が外部メディアのインタビューに答えていたり、あるいは業界の有識者が分析しているレポートがあったりして会社ホームページ以外に情報が載っているケースもあります。
そうした自社が直接発表している情報以外であっても、自力で探せる情報であれば全て調べて把握しておくことで、不必要な質問を避けることができます。
まとめ
最終面接は選考プロセスの最後であるという点よりも面接官が誰であるかの方が対策する上では重要な要素となります。
対策にあたっては、まず最終面接に出てくる人が誰なのかを企業やエージェントに聞くようにしましょう。
基本的には役員クラスの方が面接官で出てくるはずで、見られるポイントは細かなスキルよりも人物面であることが多いです。
ただし、面接官自身がハンズオンで業務に携わっている場合には実務への理解が深いことから質問もスキルの確認が中心になる可能性があるので注意しましょう。
なので、面接官を調べる際にはこれまでの経歴を合わせて聞いておくことで、ある程度聞かれそうなことや、こちらから聞くべきことを整理する参考になります。

















