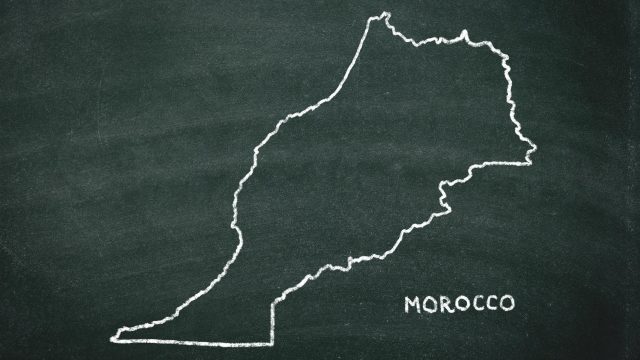駐在員に興味があるけど赴任期間はどれくらい長いのかな?
海外駐在を言い渡された。できれば行きたくないけど何年我慢すればいいのか知りたい。
駐在期間の平均は3〜5年が多いが、場合によっては半年で帰任させられる場合も。
人材不足の企業では帰ってこれない場合もある。
私は転職エージェントでグローバル案件に数多く携わってきました。その経験をもとに、海外駐在員の赴任期間がどれくらいで、どんな事情の時に期間が変動するのかについてシェアさせていただきます。
合わせて読みたい:【最新版】海外駐在員を目指す人のための情報まとめ【随時更新】
海外駐在期間の平均は3〜5年
海外駐在の期間は大体3年から5年であることが多いです。
3〜5年である理由はいくつかありますが、一つは海外駐在を育成目的と置いている企業が多いことが挙げられます。
駐在期間は3〜5年と社内の規則で定めている企業が多い
海外に赴任すると日本での役職よりも責任あるポジションを任されることが普通であり、その結果、海外駐在の経験を通じてスキルや経験を身につけることができます。
そうして将来的には日本本社の幹部として力を発揮してほしいと会社は考えているのです。
また、育成目的とは別に、家族がいる場合だと長期間にわたる単身赴任や家族同伴での海外生活は従業員にも家族にも負担が大きいこともあり、数年を上限としている場合もあります。
駐在期間を定めている理由は本人や家族の負担、育成期間の目安として考慮された結果であることが多い
3年の場合だと赴任して現地に慣れるまで半年〜1年、次の駐在員がきて引き継ぎをきちんとするまでに数ヶ月かけることを考えると、ちゃんと戦力として活躍できる期間はそれほど長くありません。
短い時間でキャッチアップするとともに、駐在員が変わっても会社が成長し続けられるように現地法人の事業や組織を作り上げることが求められます。
駐在員が苦労した体験は以下の記事でご紹介しています。

短期間で海外駐在が終わるのはどんな理由?
中には駐在して半年で帰任するケースもないわけではありません。
理由は主に3パターンあります。
・駐在員が海外での生活に耐えられない
・家族の問題
・赴任先からNGを貰う
駐在員が現地での生活や仕事に耐えられなくなる
日本で課長だったのに海外拠点では社長を任されるなど、これまでよりも重い責任を負わされるのに加え、慣れない海外での生活のストレスも合わさる中で数年いるのは耐えられないというケースはあります。
つまり本人都合の問題ですね。
特に生活のインフラが整備されていない新興国ほどこうしたストレスに悩む駐在員の方は多くなってきます。
奥さんや子供など家族の問題
本人は大丈夫でも家族側の問題で帰任を余儀なくされるケースも多いです。
単身赴任の場合には離れ離れの生活でストレスがかかったり、家族と一緒に海外に行く場合でも駐在員同士の家族付き合いのストレスなどもあります。
駐在に伴う主なストレスについては以下の記事で解説しています。

現地法人側から追い出される
時に駐在員のスキル不足などを理由に現地従業員から本社にクレームが行ったりして次の駐在員と交代させられることもあります。
海外駐在が初めてだとどうマネジメントして良いかわからず、つい日本の文化を押し付ける形で「残業しろ!」みたいに現地の価値観に合わないことをしてしまったり、現地のスタッフを下に見るような言動が引き金となることが多くあります。
いくら日本で実績を出せていたとしても、海外で同じように受け入れられるかどうかは別問題です。
本社から派遣される立場(駐在員)ではなく現地採用されている人がどんな気持ちで働いているのかはこちらの記事を参考にしてみてください。

長期間に渡って海外駐在が続くのはどんな理由?
3〜5年どころか中には20年以上も海外駐在を続ける人もいます。
これは3年で駐在員を交代させようにも代わりに日本から派遣できる人材が揃っていない場合に、駐在期間が長期化するのです。
一つの国にずっといるケースもあれば、複数の国を渡り歩く人もいます。
このような場合、日本に戻ってきても逆に日本での働き方に馴染めない人も多く、帰任したタイミングで退職することが珍しくありません。
詳しくはこちらの記事で解説しています。

また、海外駐在が長引いた場合、その経験を元に転職活動をすると企業からどういった評価を受けるのかについてはこちらの記事をどうぞ。

海外駐在員になるには?
今いる会社で海外駐在のチャンスがない場合、転職でその機会を掴むほかありません。
しかし、現実には駐在を前提とした求人はそれほど多くないので、出てくるタイミングを逃さないことが重要です。
こちらの記事を参考にしてみてください。

駐在員になるのであれば語学力は必須条件です。
もしまだ語学力に自信がないのであれば早期に身につけておきましょう。
3ヶ月もあれば十分にレベルを引き上げられますので、駐在員になるチャンスを高めたい方は以下の記事を参考にしてみてください。
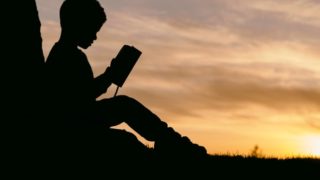
また、まだ転職エージェントへの登録がお済みでない方は転職エージェントに登録をしておき、駐在前提の求人が出たら紹介してもらえるようにしておきましょう。
使うべきエージェントについては以下の記事を参考にしてみてください。

合わせて読みたい:【最新版】海外駐在員を目指す人のための情報まとめ【随時更新】