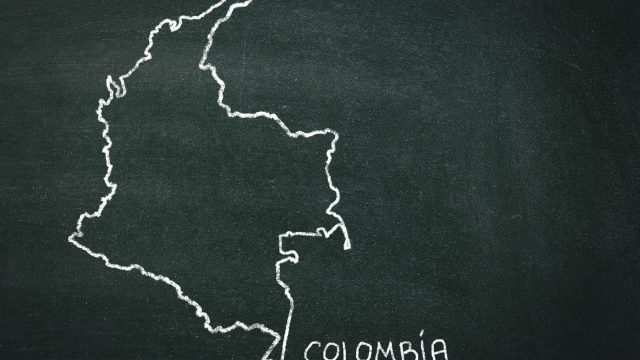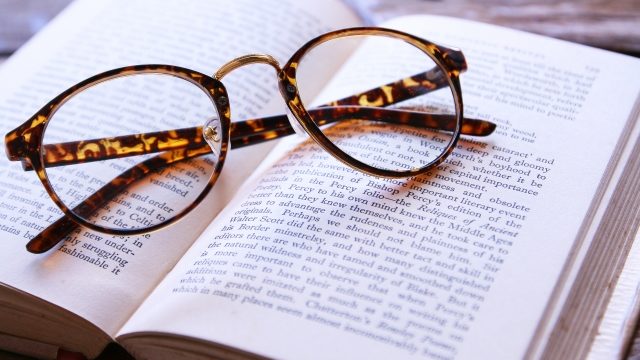・海外駐在に憧れてるけど実際に駐在している人はどんな理由で辞めちゃうのだろう?
・今海外に赴任中だけど転職を考えている。自分と同じような人って他にもいるの?
駐在員がどんなきっかけ、理由で転職を考えるのか具体的にご紹介いたします。
私は転職エージェントで海外駐在経験者の方とたくさんお話しする機会をいただきました。その経験から、海外に行った人が転職を考えるきっかけについて聞いたお話をシェアさせていただきます。
華やかなイメージのある海外駐在員ですが、実際にはそのチャンスを掴んでも退職してしまう人が多くいるんです。
結論から言えば、駐在員の退職理由は「日本に早く帰りたいから退職する」と「日本に帰りたくないから退職する」に分類できます。
具体的に紹介していきますね。
もし駐在員になる方法が知りたい方は↓の記事をご覧ください。
合わせて読みたい:【最新版】海外駐在員を目指す人のための情報まとめ【随時更新】
海外駐在が合わず早く日本に帰りたいケース
まずは海外駐在で働くことが自分に合わなかったケース。そこからさらにいくつかのパターンに細分化されますので、順番にご紹介していきます。
海外駐在期間の終わりが見えず退職
駐在期間は一般的に3〜5年限定というのが多いですが、一度海外に赴任すると20年以上行きっぱなし、ということが珍しくありません。
単身赴任であることも多いので、20年ほとんど家族と会わない生活を強いられるのが苦痛という方が出てきます。
本社に帰りたいと要請しても「もう少しだけ頑張ってくれ」と言われ続けて具体的なアクションがないまま何年も経つうちに気持ちが折れてしまうのです。
特に中小〜中堅企業では、海外駐在から戻そうにも代わりに海外に送り出せるような人材が揃っていませんので、海外駐在が長期化しがちです。
逆に長く海外で働きたい人は人材不足の企業を選んだ方が良かったりします。
また、大企業でも海外事業があまり進んでいない企業では同様のことが起こります。
もっと言うと、たとえ代わりに無理やり誰かを海外に送り込んだとしても、その人材がうまくいかなかった場合、経営判断ですぐまた元いた人が海外に派遣されることになると言うパターンも多くあります。

治安への不安から退職
先進国ならまだしも、途上国へ赴任されている方は治安の面で不安を感じ転職を希望されるケースがあります。
特にアフリカや中南米に赴任している方がこうした理由で転職を考える傾向にあります。
ここ5年でいえば自動車部品メーカーを中心にメキシコへ拠点を出す日系企業が増えました。
つまりメキシコ駐在員が増えたのですが、現地の治安を懸念して帰国したがる人が一定数出てきています。
過去にプラントエンジニアリング会社では実際に被害者が出ていますしね。
海外駐在の場合、単身赴任であればまだしも家族帯同の場合には家族の安全が優先です。
少しでも危ない目にあったり立て続けに事件が起こったりすると転職を考えるきっかけとなりがちです。
企業としてはこうした地理的な危険度の高さに応じて駐在手当の金額も高く設定するのが一般的です。
でもお金で命は買えませんので、そうした好待遇を捨てても日本に帰国したいと思う人は多くいるのです。

駐在員の家族が海外生活に合わずに退職
自分自身は海外生活を楽しんでいても、家族が合わずに帰国する道を選ぶ方もいます。
これは単に現地の食事や文化が合わないというだけでなく、駐在員の家族同士の付き合いという狭いコミュニティーの人間関係に嫌気が差すケースもあります。
奥さんが現地の人とも交流できる語学力や性格でない場合には特にコミュニティ内での人間関係が重要になります。
駐在員の家族のメンタルケアをサービスとして提供する企業があるくらいですので、家族帯同で海外赴任する場合には深刻な問題になり得ます。
子供を日本で育てるために退職
子供の教育に関する問題は転職理由ではよくみられることです。
今回の例で言えば、子供を海外で育てるのか日本で育てるのかという教育方針によって転職せざるを得ない場合が出てきます。
将来的に日本に帰るつもりなのであれば、長いこと海外で育ててしまうと日本での生活に馴染めなくなる可能性があるとの判断から、子供がまだ小さいうちに帰国する道を選ぶ家族も多いです。
逆に海外で育てると結論を出す場合には、帰任命令が来たタイミングで現地に残るべく転職することになります。
また、海外で学ばせる場合にはインターナショナルスクールに通わせたいと願う人が多くいます。
でも、いくら駐在員であってもインターナショナルスクール代は自己負担というケースもあり、待遇改善を希望して転職するケースもなくはありません。
最近は駐在員の待遇を見直す企業も増えてきており、インターナショナルスクール代を企業が負担する割合は減ってきています。
ちなみに子供が幼少期に海外で過ごすと英語や現地後を身につけてしまい、日本語能力が発達しないことがあります。
そうなってから日本に帰国した場合、普通の日本の学校に通わせるといじめに発展するリスクもあり、国内でもインターナショナルスクールに通わせる必要が出てくる場合があります。
合わせて読みたい:【最新版】海外駐在員を目指す人のための情報まとめ【随時更新】
本社の方針に反発して辞める
駐在員が現地法人で仕事をする上で日本本社が障害となることがあると言ったら驚く方もいらっしゃるかもしれません。
例えば、採用の面で言えば海外では日本よりも選考を素早く行う必要があります。
海外で選考に1ヶ月もかけていては候補者に逃げられてしまいます。
にも関わらず本社も面接したいと言い出し、選考に時間がかかった挙句優秀な候補者に逃げられるなんてことは珍しくありません。
また、しっかりした事前のリサーチもなく社長の思いつきで海外に進出しただけなのに早く成果を出せとプレッシャーをかけられます。
なのに十分な投資はしてくれない、というような不満を持つ場合もあります。
海外事業に不慣れな会社では本社に海外経験者がおらず、現地の事情がわからないが故に適切なサポートを行えない企業が大半です。
海外に赴任する場合には孤独な戦いを強いられることがほとんどであることを肝に命じておいた方が良いでしょう。
逆に社長や役員に海外駐在経験者がいると心強いです。
海外拠点に赴任すると、駐在員は現地法人の管理職、時には社長というポジションで仕事をすることになります。
慣れない食生活、知り合いもいないストレスフルな環境での勤務に加え、ビジネスの面でも(主に東南アジアで)遅刻するのが当たり前の社員、不正をする社員、賄賂を要求してくる役人など、日本とは事業環境が全く異なります。
現地での駐在員が遭遇する事件についてはこちら↓の記事で紹介しています。

給料一つとってみても、日本では年間の昇給率などたかが知れたもの(企業によってはゼロ)ですが、東南アジアでは毎年5〜10%上がるのが当たり前なのです。
優秀な現地従業員をつなぎとめようとするには10%以上昇給させないといけません。
しかし本社は「まだ黒字にもなってないのに人件費を上げるなんてもってのほか」として許してくれません。
そんな現地従業員と日本本社の間に板ばさみとなり精神が参ってしまう人や、本社への怒りから愛想をつかして辞めてしまう駐在員は珍しくありません。
海外駐在を元気に乗り越えられる人というのは、現地法人側の立場で現地に寄り添って仕事をしながら本社の命令をあしらえる人です。
または、本社の立場を貫き通して現地法人に感情移入しすぎず冷静に乗り切れる人のどちらかというのが個人的な印象です。

駐在期間が終わっても日本に帰りたくないケース
続いて、海外駐在員として働くことが好きで日本に帰りたくないケースがあります。
その典型的なパターンを紹介していきます。
帰任命令が来たけどその国での生活を続けたい
冒頭で述べたように、駐在員の赴任期間は3〜5年です。
いくら本人が長期にわたる海外赴任を希望したとしても、多くの場合には期間が来れば日本に戻されることになります。
しかし、数年生活する中でその国のことが好きになり、引き続きその国で生活していきたいという気持ちが出てきます。
ASEAN地域、特にタイやベトナムの駐在員に多くみられる傾向があります。
アフリカのように現時点での生活インフラが未整備な国での駐在経験者はあまりこの理由で転職をしません。
タイやベトナムのように、今まさに成長段階にあり、日本にはない活気が感じられる国で、かつそこそこ生活しやすいという国で駐在している人が引き続きその国で生活したいという気持ちになるようですね。
退職を機に、現地での人脈を生かしてコンサル事業など個人でビジネスを始める人も少なくありません。
同じく駐在員など日本人同士の人間関係ができているので、そのコミュニティ内でビジネスが回せてしまうようです。
現地駐在員の決済でOKを出せる範囲で商品・サービスの金額を設定すると円滑に話が進むと言っていた人がいました。
日本本社に戻ると裁量の大きさとスピード感が失われるという不安から退職
赴任先の国自体が好きというよりは、自身のキャリアや仕事内容の観点で転職を考える方も多くいます。
駐在員として赴任する際は日本にいた時よりも高い職位で仕事をすることが一般的です。
基本的には2階級ほど上の役職を任されることが多いです。
例えば本社の部長級の人が海外で社長になったり、日本での主任級の社員が海外で部長になったりします。
また、海外では日本に比べて法律やルールが未整備であることが多く、良く言えばビジネスの自由度が高いため、役職の高さと相まって海外では日本にいた時よりも大きな裁量で仕事を進めることができるのです。
海外拠点では部長や役員、社長として大きな権限を持って仕事を進められていたのに、帰国後は役職が下がって仕事をすることになります。
これは個人にとってはキャリアダウンにも感じられるほどモチベーションを下げる要因となります。
また、海外では日本のように一旦社内に持ち帰って全会一致で賛成が取れるまで行動できないというようなことがなく、スピード感を持って仕事を進められる環境であることも魅力に移ります。
根回し文化や意思決定の遅さは外国人が日本を働く場所として選ばない理由にもなっています。
そうした裁量とスピード感とにやりがいを感じる駐在員は多くいるのですが、それが一度日本に帰任してしまうと、再び保守的でスピード感もなく、自分自身の裁量も狭くなる環境が待っています。
海外ではその日のうちに決断していたことが本社では1ヶ月経ってもまだ議論を続けている、というような石橋を叩いて叩き壊す環境に嫌気がさして退職を考えるようになるのです。
駐在員が帰国後に辞める理由の半分は、海外駐在の経験を十分に活かせないポジションを任されたためです。
多くの日系企業では海外で経験を積んだ人材を国内でどう活用すべきかについて十分に考えていません。
その結果、海外と何の関係もない国内営業拠点の支店長ポストを任せたりします。
それが本人の希望であれば何の問題もありませんが、多くの場合、海外駐在の経験者は直近の経験である海外事業に関わる仕事をしたいと考えるのが普通です。
また、海外関連だとしても海外拠点の管理だけを任されるケースもやりがいを感じずらく、もっと事業を成長させていく実感を得られるポストを希望して退職するケースが多く見られます。

現地採用でも良いから再び海外に行きたくなる
海外駐在時の仕事が気に入った方は駐在員としてのチャンスを再びつかむべく転職活動を始められます。
しかし、結果的にそのチャンスを掴めなかった場合、待遇が悪くなっても海外で働くことを重視して現地採用で転職する方も珍しくありません。
それくらい日本と海外とでは労働環境が異なるのです。
もちろん、海外と一括りにできるものでもなく、アメリカとイギリスでは異なりますし、タイとベトナムとでも異なります。
しかし、それでもやはり日本とそれ以外、というくくりかたをしても差し支えないほど日本は特殊な労働慣行が残っているのかもしれません。
それくらい数多くの方が海外経験後に帰国しても再び海外へ旅たちます。
一度しかない人生ですから、海外で働くことにチャレンジしてみても良いかもしれません。
合わせて読みたい:【最新版】海外駐在員を目指す人のための情報まとめ【随時更新】
将来駐在員になりたいなら何をすべき?
将来駐在員を目指すなら、海外駐在員になりやすい企業へ転職することと、そのために必要な語学力を身につけることが重要です。
まだ英語力に自信がない方は英語力の向上から始めましょう。
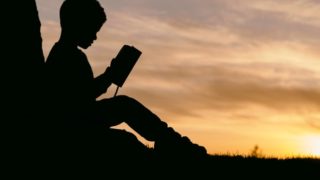
もし英語力をお持ちの方であれば、転職活動を始めても大丈夫です。
駐在前提の求人は極めて数が限られるため、早めに登録だけでもしておかないと良い案件に出会える可能性がさらに減ってしまいます。